
お遍路は自転車で!準備・費用・ルートを解説
こんにちは。幸せのかたちの運営者です。
四国八十八箇所のお遍路を、自転車で巡ってみたいと考えたことないですか?歩き遍路よりも速く、車遍路よりも深く。自転車遍路は、そんな魅力的な巡礼のスタイルです。
ただ、いざ計画しようとすると、どんな自転車を選べばいいのか、ロードバイクやE-BIKE(電動アシスト自転車)はどっちがいいのか、迷いますよね。また、具体的な装備や持ち物、費用の目安、どれくらいの日数が必要なのか、そして何より「遍路ころがし」と呼ばれる難所のルートは大丈夫なのか、不安も多いでしょう。
この記事では、自転車でお遍路を考えている方に向けて、準備段階から実際のルート攻略、サイクリスト向けの宿の情報まで、必要な情報を解説します。自転車遍路のブログ体験談なども参考にしつつ、皆さんの計画のヒントになれば幸いです。
- 自転車遍路のメリット・デメリットと車種選び
- 必要な装備、費用、日数の目安
- 「遍路ころがし」など難所ルートの攻略法
- サイクリスト向けの宿や荷物戦略
お遍路を自転車で巡る準備

お遍路を自転車で巡ると決めたら、まずは準備からですね。歩き遍路とも車遍路とも違う、自転車ならではの準備が必要です。装備、自転車の選定、費用感、日数など、計画の土台となる部分を、詳しく見ていきましょう。
メリットとデメリット
自転車遍路を選ぶ理由は人それぞれですが、他の手段と比べたメリットと、覚悟しておくべきデメリットを知っておくことは大切です。
最大のメリットは、やはりその「機動性」と「程よい速度」でしょう。
歩き遍路(徳島県観光情報サイトによると45日程度(出典:徳島県観光情報サイト阿波ナビ「四国遍路に出かけよう」)、資料によっては55日程度ともされ、おおむね40日~55日程度)ほど時間はかからず、車遍路(約10日)ほど速すぎない。目安として15日~20日程度と言われますが、自分の体力や目的に合わせて日程を調整しやすいのは大きな魅力です。車ではあっという間に通り過ぎてしまう沿道の風景や、旧遍路道(舗装されている場合)、細い道にもアクセスしやすい。地域の方との距離感も絶妙で、歩き遍路の方と同じように「お接待」の文化に触れる機会も多いでしょう。
一方で、デメリットも明確です。ここはしっかり向き合っておく必要があります。
自転車遍路の主なデメリット
- 物理的な厳しさ(激坂) 四国は山が多く、お寺も山の上に点在しています。特に「遍路ころがし」と呼ばれる激坂は、荷物を積んだ自転車にとっては想像以上の厳しさになることがあります。
- 天候の影響 雨天時の走行は、視界が悪くなるだけでなく、体温低下やスリップのリスクが格段に上がります。夏の猛暑は熱中症、冬は寒さや路面凍結(特に山間部)との戦いになります。
- メカニカルトラブル パンクはほぼ必ず経験すると言ってもいいでしょう。他にもチェーン切れや変速機の不調など、自分で対処(あるいは自転車店を探す)する必要があります。
- 交通上の危険箇所 後述しますが、歩道のない狭いトンネルや、交通量の多い国道を大型トラックと並走する区間など、特有の危険が伴います。
- 荷物の制約 歩き遍路よりは多く持てますが、車遍路のように何でも持っていけるわけではありません。荷物の重さがそのままペダルの重さに直結します。
これらの課題を「どう乗り越えるか」を具体的にシミュレーションしておくことが、安全な結願への第一歩です。
E-BIKEとロードバイク比較
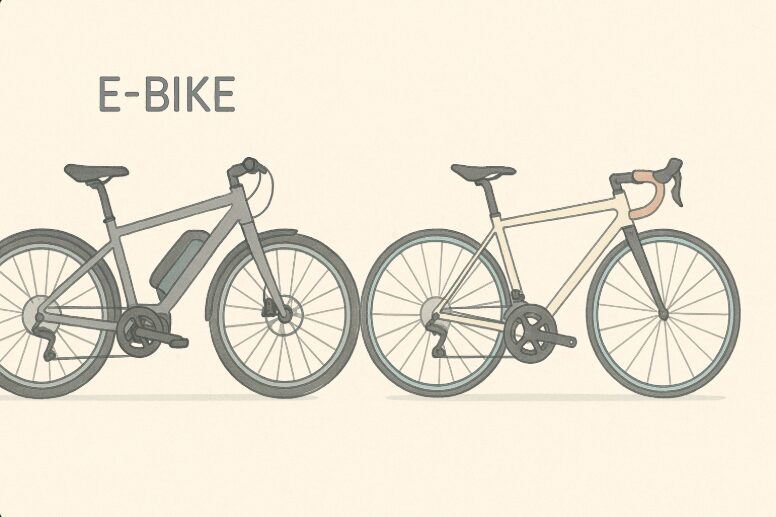
自転車遍路で最も悩むのが、「どの自転車で行くか」という機材選定ですよね。それぞれに一長一短があり、ご自身の体力や目的によって最適な選択は変わってきます。
E-BIKE(電動アシスト自転車)
近年の技術革新で、E-BIKEは自転車遍路において非常に有力な選択肢になっています。特に「最強」とも評される第60番横峰寺のような激坂を登る際のアシスト力は絶大です。
体力的な負担を大幅に軽減してくれるので、体力を温存し、お寺での参拝により集中できるという精神的な余裕も生まれます。体力に自信がない方や、登り坂での苦行よりも巡拝そのものを重視したい方には、本当に心強い味方になるでしょう。
E-BIKEの注意点:バッテリーと重量 最大の懸念点は、やはりバッテリーです。航続距離は車種やバッテリー容量、走行モード、そして路面状況(勾配)、積載荷物の重量、気温などで大きく変動します。メーカー公称値は、平坦な道を想定していることが多いです。お遍路のような激坂でアシスト力の強いモードを多用すると、バッテリー消費は予想以上に激しくなります。したがって、E-BIKEを選ぶ場合は、ルート上、特に山岳地帯の麓に「充電設備を備えた宿泊施設」を確保することが、計画の前提となります。また、車体自体が重いため、万が一バッテリーが切れた場合、ただの「重い自転車」になってしまうリスクも考慮しておく必要があります。
ロードバイク・クロスバイク
舗装路での巡航性能、平坦な海岸線を長距離移動する際の効率は、やはりロードバイクやクロスバイクが優れています。軽量で、自分の力で漕いでいるダイレクト感が、達成感にもつながります。普段から乗り慣れた愛車で四国を巡りたい、という方も多いでしょう。
しかし、「遍路ころがし」と呼ばれる難所に挑むには、相応の脚力と覚悟が必要です。特にロードバイクは、荷物を積む(パニアバッグなどを取り付ける)ためのキャリア設置に工夫が必要な車種も多いです。
経験者の中には、難所の麓の宿に荷物をすべて預け、身軽な「ヒルクライム」装備でアタックするといった戦略的な工夫をされている方もいます。自分の体力を過信せず、冷静に判断することが本当に大切です。
マウンテンバイクやグラベルロードは? お遍路道には、一部「へんろ道」として登山道のような区間も残っていますが、自転車遍路は基本的に舗装路(国道や県道)を走ります。そのため、太いタイヤのマウンテンバイクは、舗装路での抵抗が大きく、長距離巡航には不向きでしょう。舗装路も未舗装路も走れる「グラベルロード」や、太めのタイヤが履ける「ツーリングバイク」は、安定性や積載性の面で良い選択肢になるでしょう。
どちらを選ぶにせよ、出発前にしっかりとメンテナンスを行い、自分の体にフィットさせておくことが重要です。
自転車の調達方法:3つの戦略

自転車をどう調達するか。これも計画の早い段階で決めておきたいですね。大きく分けて3つの戦略があると考えられます。
A. 自身の自転車の輸送(本格派・全周向け)
1,000km以上に及ぶ全周走破を目指す本格的なサイクリストの方にとっては、これが第一選択肢になるでしょう。やはり自分の乗り慣れた自転車が一番安心です。
この場合、自宅から四国のスタート地点(例:1番札所近くの宿や、今治サイクルステーションなど)へ自転車を輸送するサービスを利用します。有名なところでは、西濃運輸株式会社の「カンガルー自転車イベント便」や、BTB(Bicycle Transport Box)輪行箱を利用した宅配サービスなどがあります。これらは事前に申し込みが必要で、費用もかかりますが、愛車を安全・確実に届けることができます。もちろん、自分で輪行袋に入れて、公共交通機関(飛行機、新幹線、フェリーなど)で運ぶ方法もありますが、かなり大きな荷物になります。
B. フルサポート・レンタル(体験・短期向け)
「全周は難しいけど、お遍路の雰囲気や文化を体験したい」という方には、現地でのレンタルサービス、特にツアー形式のものがおすすめです。例えば、「サイクリングで気軽なお遍路体験と日本のディープな醸造文化体験」といったプランもあります(出典:ツーリズム四国)。これだと、Eバイクのレンタルだけでなく、宿坊での宿泊や精進料理、地域の文化体験までパッケージ化されているようです。走行距離も比較的短く、難易度も抑えられているので、観光目的やウェルネス・ツーリズムとしてお遍路に触れたい方には最適でしょう。
C. 区間限定シェアサイクル(ハイブリッド遍路向け)
これは、比較的新しいスタイルです。四国全土をカバーするものではありませんが、特定のエリアでシェアサイクルが導入されています。
これは、全行程を自転車で走るためではなく、例えばJRと徒歩遍路を組み合わせて巡る方が、公共交通機関でのアクセスが不便な特定の区間だけ自転車を利用する、といった「ハイブリッド遍路」を可能にするものです。
ご自身の目的(全周か、体験か)、日数、予算に応じて、最適な調達方法を選んでみてください。(出典:HENROレンタサイクル)。
必要な装備と持ち物リスト
自転車遍路は、「お遍路さん」としての装備と、「サイクリスト」としての装備、その両方が必要になります。荷物はできるだけ軽量化したいですが、安全に関わるもの、そして巡拝に必須のものは削れません。
ここで、それぞれの装備を具体的にリストアップします。
お遍路さんの基本装備(巡拝用品)

これらはお寺での参拝、そして納経(御朱印)をいただくために必須のものです。
- 納経帳、または納経軸:御朱印をいただくためのものです。
- 白衣(はくえ):納経帳とは別に、白衣に御朱印をいただくこともできます(両方いただく場合は納経料もそれぞれ必要です)。
- 輪袈裟(わげさ):お遍路さんの正装とも言えるものです。参拝時は首にかけます。
- お数珠(じゅず):合掌する際に使います。ご自身の宗派のもので大丈夫でしょう。
- お賽銭:各お寺で本堂と大師堂、最低2ヶ所でお参りします。5円玉や1円玉を多めに用意しておくと、スムーズです。
- お線香・ろうそく・ライター:これも本堂と大師堂でそれぞれお供えします。束で持っていき、お寺で小分けにできる携帯ケースがあると便利です。
- (金剛杖・菅笠):この2つは自転車遍路では悩ましいところです。金剛杖は弘法大師様の化身とも言われますが、自転車での運搬は非常に困難です。短いものを選ぶか、持たずにお参りする方もいるようです。菅笠も、ヘルメットと併用できないため、安全を最優先しヘルメットを着用することを推奨します。
お遍路の持ち物や、納経帳については、以前に書いた記事がありますので、よろしければそちらも参考にしてみてください。
サイクリストとしての装備(安全・走行用品)

こちらは、長距離を安全に走破するための装備です。
- ヘルメット(強く推奨):これは万が一の時に命を守るものです。必ず着用しましょう。※日本では自転車乗車時のヘルメット着用は努力義務です。
- 強力なライト(前後):特にリアライト(尾灯)は、トンネル対策として非常に重要です。日中でも常時点滅させ、予備電池や充電体制も万全に。
- パンク修理キット・携帯工具・予備チューブ:パンクは起きるものとして、自分で修理できる準備をしておきましょう。
- 鍵(ロック):高価な自転車を、参拝中に目の届かない場所に置きます。盗難対策として、軽量なワイヤーロックだけでなく、U字ロックや堅牢なチェーンロックの携行を強く推奨します。
- レインウェア:上下セパレート型で、防水透湿性の高いものが快適です。コンビニのポンチョでは太刀打ちできません。
- サイクルウェア:汗をかいてもすぐ乾くインナーや、お尻の痛みを軽減するパッド付きのパンツがあると快適さが全く違います。重ね着(レイヤリング)で体温調節できるようにしましょう。
- グローブ:手のひらの疲労軽減や、転倒時の怪我防止になります。
- スマートフォン(ナビ用)・モバイルバッテリー:地図やナビ、宿の検索、緊急連絡に必須です。バッテリー切れは致命的になりかねません。
- 補給食・ドリンクボトル:エネルギー消費が激しいので、すぐにつまめる行動食(羊羹、ナッツ、エナジーバーなど)を常備しておきたいですね。
これら全てを運ぶことになります。荷物の積載方法(バックパック、サドルバッグ、パニアバッグなど)も、ご自身の自転車に合わせてよく検討してみてください。
費用の目安と内訳
自転車遍路にどれくらい費用がかかるのか、これは計画を立てる上で非常に重要なポイントです。「何日間かけるか」と「どんな宿に泊まるか」で総額は本当に大きく変わってきます。
あくまで一般的な目安ですが、15日~20日の日程で、総額15万円~25万円くらいを見ておくと現実的でしょう。ただし、宿泊形態や日数、食費のかけ方で大きく変動します。
主な内訳を詳しく見てみましょう。
お寺に納める費用(固定費)
これは、どなたでも(ほぼ)共通でかかる費用です。納経料は2024年4月1日に改定されました。
2024年4月1日改定後の主な納経料(出典:四国八十八箇所霊場会 公式サイト)
- 納経帳(御朱印):1ヶ所 500円
- 白衣(御朱印):1ヶ所 300円
- 掛け軸(御朱印):1ヶ所 700円
- 大師納経(御影保存帳用):1ヶ所 500円
- 重ね印(納経帳):1ヶ所 300円
もし納経帳だけに御朱印をいただく場合、500円×88箇所=44,000円 が最低限必要になります。白衣にもいただく場合は、さらに 26,400円 が加わります。これに加えて、最初のお寺(1番札所 霊山寺など)で納経帳や白衣などを購入する費用(数千円~)、そして各お寺の本堂と大師堂で納めるお賽銭が加算されます。
ご注意ください これらの金額は、本記事執筆時点での情報です。最新の正確な情報や、詳細なルール(例えば、掛け軸と納経帳両方の場合など)については、必ず「四国八十八箇所霊場会」の公式サイトなどでご確認いただくようお願いいたします。
宿泊費(最大の変動要因)
ここが総費用を左右する最大のポイントです。選択肢は多岐にわたります。
- 善根宿・通夜堂・野宿:0円~(寸志)。遍路文化の「お接待」の一環として無料で泊まれる場所や、お寺の境内にある宿泊所(通夜堂)などです。費用は劇的に抑えられますが、寝袋やマットといった相応の装備と、天候や安全管理に関する高度な自己責任が求められます。
- ゲストハウス・遍路宿:1泊 3,000円~5,000円程度。相部屋(ドミトリー)が中心で、他の遍路さんとの交流も生まれやすいです。
- ビジネスホテル・サイクルお宿:1泊 6,000円~10,000円程度。個室でプライバシーが守れ、洗濯や自転車保管(サイクルお宿の場合)の設備が整っていることが多いです。
- 宿坊(2食付き):1泊 7,000円~12,000円程度。お寺に宿泊し、精進料理をいただいたり、朝のお勤めに参加できたりと、貴重な体験ができます。
安全と快適さを取りつつ費用を抑えたいなら、ゲストハウスやビジネスホテルを基本にし、何日かは宿坊に泊まってみる、といった組み合わせが良いでしょう。
食費・補給費・その他
自転車遍路は、徒歩遍路以上にエネルギー消費が激しい(特に山岳地帯)ため、食費や行動食(補給食)の予算は多めに見積っておく必要があります。1日2,000円~3,000円程度は見ておきたいところです。
これらに加え、自宅から四国までの往復交通費、自転車の輸送費、ロープウェイ代(太龍寺など)、途中のメンテナンス費用(パンク修理など)が加わって、総額となります。最新の料金は各公式サイトで確認しましょう。
必要な日数のモデルケース
「何日間あれば結願(けちがん:88箇所すべて巡り終えること)できますか?」というのも、よくある疑問です。これは本当に、その方の体力、目的、選ぶ自転車(E-BIKEか否か)によって全く変わってきます。
四国一周のサイクリングルートは公式に「約1,000km」(出典:Cycling Island Shikoku “CHALLENGE 1,000km”)とされています。お遍路のルートはこれとは一部異なりますが、総距離の目安にはなります。
A. アスリート型(参考値)
経験豊富なサイクリストの中には、15日未満で結願する記録もあるようですが、その走行ログを分析すると、1日130kmを超えるような長距離走行日が含まれていることがあります。これは、遍路の装備(着替えや納経用品)を積載した状態でのペースとしては、日常的に長距離サイクリングを行う上級者の記録(参考値)と見るべきです。
このペースを一般の方が参考にすると、計画に無理が生じ、疲労による事故のリスクが高まったり、お寺での参拝がただのスタンプラリーのようになってしまう可能性があります。
B. 一般・巡拝重視型(推奨):15日~20日程度
多くの方にとって現実的かつ推奨されるのがこの日数でしょう。15日から20日程度の日程です。1日の走行距離を平均60km~80km程度に設定し、途中の山岳地帯や、お寺での参拝時間(読経、納経、境内の散策)を十分に確保するイメージです。これくらい余裕があれば、道中の風景を楽しんだり、地元の方と少しお話したりする心の余裕も生まれるのではないでしょうか。
C. ゆったり・体力不安型:20日以上
体力に自信がない方、E-BIKEを使わない方、あるいは一つ一つのお寺やその土地の歴史をじっくり味わいたい方は、20日以上(例:20日~25日)かける計画を立てるのが賢明です。1日の走行距離を50km程度に抑えれば、激坂があっても、その日のうちにリカバリーしやすいでしょう。お遍路は競争ではありませんから、ご自身のペースを大切にするのが一番です。
D. 短縮・体験ルート
もちろん、全周走破(通し打ち)にこだわる必要は全くありません。
- 区切り打ち:何回かに分けて(例:4回に分けて「発心の道場」徳島だけ、など)巡るスタイルです。
- 小豆島八十八箇所:「遍路の縮図」とも言われ、5泊6日程度で巡るモデルコースもあるようです。
- Eバイク体験(香川):前述の、弘法大師空海さまのご生誕地、善通寺市周辺(71番~77番)を1泊2日で巡るプランもあります。
ご自身の時間的・体力的な制約の中で、無理のない計画を立ててみてください。ちなみに、88箇所すべてを巡り終える「結願」については、お遍路の「結願(けちがん)」とは?の記事でも少し触れています。
お遍路で自転車のルート攻略

準備が整ったら、いよいよルート攻略の計画ですね。自転車遍路は、整備されたサイクリングロードを走る観光サイクリングとは異なります。四国全土の一般公道(生活道路・産業道路)を利用するため、特有の危険が存在し、特に山岳地帯は最大の障壁となります。安全に巡拝するためのポイントを見ていきましょう。
難所「遍路ころがし」とは
お遍路の計画を立て始めると、必ず耳にするのが「遍路ころがし」という言葉です。
これは、歩き遍路の方が「転がるようにして登り下りする」ほど厳しい山道や峠道を指す、昔からの呼び名です。もちろん、これは自転車にとっても最難関のルートとなります。車であればあっという間に通り過ぎる道でも、自転車にとっては延々と続く登り坂(激坂)として立ちはだかります。
特に名前が挙がるのは、以下のお寺へ向かう道です。
自転車遍路の主な山岳難所(遍路ころがし)
- 第12番 焼山寺(しょうさんじ) 歩き遍路で「一に焼山、二にお鶴」と呼ばれる最難所。徳島県の公式サイクリングコースでも難易度「上級」とされるほどの厳しさです。
- 第20番 鶴林寺(かくりんじ) 焼山寺に次ぐ「二にお鶴」の難所。こちらも激坂が続きます。
- 第27番 神峰寺(こうのみねじ) 高知県の海抜ゼロメートル地点から、一気に標高400m強まで登る、「スペシャル」な勾配と評される難所です。
- 第60番 横峰寺(よこみねじ) 愛媛県にあり、距離、勾配、獲得標高のすべてにおいて「最強」と評されることもある最難関の一つです。
- 第66番 雲辺寺(うんぺんじ) 札所の中で最も標高が高い(標高約911m)(出典:三好市公式観光サイト)。四国八十八箇所霊場会の公式解説でも「遍路ころがしの難所」と言及されています(出典:四国八十八箇所霊場会 66番雲辺寺)。
これらの難所は、自転車で登る場合、ただでさえ厳しい上に、下りも非常に危険です。急勾配でのスピードコントロールやブレーキの負荷、路面状況(濡れ落ち葉や小石)にも細心の注意が必要になります。
山岳札所の攻略法
では、これらの厳しい山岳札所をどう攻略するか。いくつか戦略的な方法があると考えられます。
戦略1:ハブ・アンド・スポーク戦略(最推奨)
これが最も賢明で安全な戦略でしょう。前述しましたが、「毎日宿を変えながら重い荷物を積んで峠を越える」のではなく、麓の宿(ハブ)に連泊、あるいは荷物をすべて預け(デポし)、身軽な「ヒルクライム」スタイル(スポーク)で難所札所を往復するという方法です。
例えば、第60番横峰寺にアタックするなら、麓の西条市などの宿を拠点にする。第27番神峰寺なら、安田や奈半利などに拠点を置く。この戦略が使えるかどうかで、心身の負担は全く違ってくるはずです。経験者の方も、「12番、27番、60番は荷物を宿に置いてアタックした」と書かれていることが多いですね。
戦略2:ロープウェイの活用
第21番 太龍寺や、第66番 雲辺寺へは、ロープウェイが運行されています。特に太龍寺へは林道ルートもありますが、路面状況などを考えると、麓のロープウェイ山麓駅に自転車を駐輪し、乗車するのが賢明な判断でしょう。雲辺寺も、体力に不安がある場合や、時間を有効に使いたい場合は、ロープウェイ利用は現実的な選択肢です(出典:四国ケーブル 雲辺寺ロープウェイ)。
自転車のロープウェイ持ち込みについて ロープウェイへの自転車本体の持ち込み可否(輪行袋含む)については、運行会社の方針や混雑状況によって変わる可能性があります。必ず事前に各運行会社へ電話などで確認してください。
戦略3:天候の確認とハザードマップの利用
これは戦略というか、安全管理の基本です。山岳難所にアタックする日は、天候が万全の日を選ぶべきです。雨天時はもちろん、雨上がりも路面が滑りやすく、落石などのリスクも高まります。
ここで極めて重要なのが、これらの山岳札所の多くが、「土砂災害の特別警戒区域」に指定されているか、その付近を通過しているという点です。第12番 焼山寺、第27番 神峰寺、第60番 横峰寺などは、自転車遍路の「激坂」であると同時に、「自然災害のリスク」も併せ持つ場所なのです。出発前には、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」などで、走行ルートの安全性を確認することを強く推奨します。これは命に関わる情報ですので、ぜひご活用ください。
サイクリスト向けの宿の選び方
自転車遍路では、宿選びも戦略の一部です。疲労した体を休めるだけでなく、自転車のメンテナンスや翌日の準備を整える「基地」としての役割が重要になりますからね。
特に注目したいのが、「サイクリングアイランド四国」プロジェクトなどが認定・紹介している「サイクルお宿」です。
これは、四国一周(しこくいっしゅう)サイクリングを推奨するために設定された、サイクリストに優しい宿の認定制度です。認定されるには、以下の3つの必須条件を満たしている必要があるようです(出典:Cycling Island Shikoku 宿一覧)。
「サイクルお宿」必須の3つの条件
- 自転車保管場所 雨風や盗難から大切な自転車を守るための、屋内または安全な保管スペースが提供されていること。
- ランドリー施設 汗や泥で汚れたサイクルウェアを洗濯・乾燥できる設備(洗濯機・乾燥機)があること。
- スポーツサイクル用の空気入れ 仏式バルブなどに対応した、スポーツサイクル用の空気入れの貸し出しがあること。
これらに加えて、「あるとうれしいおもてなしサービス」として、メンテナンススペースや工具の貸し出し、自転車の配送サービス(次宿への転送など)に対応している宿もあるようです。公式サイト掲載例として、愛媛県の今治プラザホテルや、香川県のささや旅館などがあります。
山岳難所の麓で、前述の「ハブ・アンド・スポーク戦略」を実行するためにも、こうした「サイクルお宿」や、荷物預かりに柔軟に対応してくれる宿を事前にリサーチし、予約しておくことが、快適な巡拝の鍵になります。
徳島市にある「guesthouse CYCLE&STAY」(出典:自転車旅/レンタサイクルについて(guesthouse CYCLE&STAY))のように、自転車旅の拠点としてレンタサイクルなどを提供している施設もあります。荷物預かり等のサービスについては、各施設へ事前に問い合わせて確認しましょう。
荷物デポ戦略がおすすめ
この「荷物をどうするか」というロジスティクス(兵站)の問題は、自転車遍路の快適性、ひいては安全性を左右する最重要課題の一つです。
重い荷物(着替え、納経用品、輪行箱など)は、疲労を蓄積させ、激坂の難易度を劇的に上げ、パンクのリスクを高めます。この問題を解決する方法として、やはり「荷物デポ戦略(荷物を預ける)」を軸に考えることを推奨します。
具体的には、いくつかのパターンが考えられます。
1. 拠点デポ(ハブ・アンド・スポーク)
山岳地帯(徳島、高知、愛媛の難所)では、これが最も有効な戦略です。何度も触れていますが、麓の宿(サイクルお宿やゲストハウス)に連泊、あるいは荷物を預かってもらい、身軽な状態で難所札所を日帰りで往復(ピストン)するスタイルです。安全マージンを最大化できます。
2. 宿泊施設間の当日配送
四国(特にしまなみ海道周辺で発達していますが)では、サイクリスト向けの荷物配送サービスも存在します。例えば、佐川急便による「手ぶらサイクリング」など、民間の配送業者が提携する宿から宿へ、手荷物を当日配送してくれるサービスです。四国遍路全周において、これらのサービスが全区間で利用可能かは事前の確認が必要ですが、平坦な区間が続く日などに活用できれば、疲労軽減に極めて有効です。ただし、毎日利用すると当然ながら費用はかさみます。
3. 全装備積載(伝統的なツーリングスタイル)
もちろん、全ての荷物を自転車に積載し、毎日宿を変えながら進む伝統的な「ツーリング」スタイルも可能です。このスタイルのメリットは、宿の予約などに縛られず、自由な行程を組みやすい点にあります。しかし、デメリットは前述の通り、荷物の重さが常につきまとうこと。このスタイルを選ぶ場合は、装備の徹底的な軽量化(ウルトラライト)が前提となりますし、山岳難所では相応の苦労を覚悟する必要があります。
ご自身の体力や、どの程度の快適性・安全性を求めるかに応じて、これらの戦略を組み合わせていくのが現実的でしょう。
危険なトンネルの注意点

自転車遍路を経験した多くの方が、山岳地帯の「激坂」と並んで、あるいはそれ以上に危険だったと指摘するのが、「歩道のない国道のトンネル」です。
これは、しまなみ海道のような整備されたサイクリングロードに慣れていると、そのギャップに驚くでしょう。四国の国道、特に海岸線や山間部を貫くルートには、生活や産業(大型トラック)のために作られた、古くて狭いトンネルが数多く存在します。
トンネル内の具体的な危険性
- 強烈な風圧と騒音 路側帯が非常に狭い、あるいは存在しないトンネル内で、大型トラックやバスが高速で真横を通過すると、強烈な気流(風圧)で車体ごと吸い込まれそうになる感覚に陥り、非常に危険です。
- 視認性の問題 トンネル内は暗く、外光との明暗差で、自動車の運転手から自転車の存在が認識されにくいです。特に雨の日などは最悪です。
- 閉塞感と騒音 轟音が反響する閉鎖空間は、精神的にも大きなプレッシャーとなります。
この問題は、国土交通省四国地方整備局も「歩き遍路や自転車遍路を想定した事業」として認識しており、安全対策を推進しています。
具体的には、以下のような対策が実施されています。
- 視認性の向上:トンネル内壁を白く塗装(例:国道56号 焼坂トンネル)したり、照明を増設して、内部の視認性を向上させる。
- 注意喚起:トンネル手前での「歩行者あり」などの注意喚起案内板の設置。
- 走行空間の明示:路面への高視認性区画線や減速マークのペイント。
(出典:国土交通省四国地方整備局)
これらの対策は進められていますが、巡拝者側も「危険な場所を通らせていただく」という意識で、最大限の自衛策を講じる必要があります。
巡拝者が講じるべき自衛策(強く推奨)
- 強力なリアライト(尾灯):日中でも必ず常時・点滅させること。予備電池やモバイルバッテリーでの充電も万全に。
- 反射材の着用:反射ベスト(工事現場で使うようなものでも可)や、リストバンド、アンクルバンドなど、目立つものを着用する。
- ヘルメットとフロントライト:当然ですが、必ず着用・点灯しましょう。
- 迂回路の検討:可能であれば、交通量の多い国道トンネルを避け、旧道や迂回路がないか事前に地図で徹底的に調べる。
安全に関わる装備だけは、妥協しないようにしましょう。
札所での駐輪マナー
無事にお寺に到着した後、もう一つ考えなければならないのが、「自転車をどこに停めるか」と「盗難対策」です。
八十八箇所の各札所において、自転車の駐輪に関する統一されたルールは存在しません。対応はお寺によって様々です。
まず大原則として、仁王門をくぐった先、神聖な境内への自転車の乗り入れは、原則として不可の寺院が多いです。現地の指示・掲示に従いましょう。多くの場合、山門の手前や、自動車用の駐車場の片隅に、指定された駐輪場所があるか、駐車場の係員の方の指示に従うことになります。
ここで最も心配なのが、盗難のリスクです。
ロードバイクやE-BIKEは、非常に高価なものです。そして、お遍路の参拝は、山門から本堂、大師堂と巡り、納経所で御朱印をいただくまで、短くても15分、長いお寺(例:山頂の本堂まで数十分歩く場合もあるお寺)では1時間以上、自転車から目を離すことになります。
その間に、大切な愛車が盗難に遭ってしまっては、巡礼どころではありません。装備として、軽量なワイヤーロック(いわゆる「地球ロック」ができない細いもの)だけでは、プロの窃盗犯には簡単に切断されてしまいます。
フレームと、地面に固定された動かないもの(柱や頑丈な柵など)を確実に繋ぐことができる、堅牢なU字ロックやチェーンロックを必ず携行することを、強く推奨します。少し重くなりますが、安心感には代えられません。
お遍路を自転車で楽しむコツ
ここまで、お遍路を自転車で巡るための準備や、厳しい点、注意点について、かなり詳しくまとめてみました。大変なことばかりのように思えてしまったかもしれませんが、これらの課題をしっかり認識して、対策を立てて臨めば、自転車遍路は本当に素晴らしい体験になるでしょう。
歩き遍路では何日もかかる距離を、風を切って一日で走り抜け、車遍路では見落としてしまうような小さな祠や、道端のお地蔵様に気づいて手を合わせる。自分の力でペダルを漕いで進み、四国の豊かな自然(時には厳しさ)を肌で感じ、お大師様(弘法大師空海)とのご縁を結んでいく…。
自転車遍路を最高のものにするためのコツは、結局のところ「無理をしないこと」に尽きます。
アスリートのように速く走破すること(結願)だけが、お遍路の目的ではありません。それは数あるスタイルの一つに過ぎません。
「今日はしんどいな」と思ったら、予定していたお寺の手前で宿を取る勇気。天候が荒れそうなら、アタックを諦めて停滞する判断力。激坂に心が折れそうになったら、自転車を押して歩く選択。時にはロープウェイや公共交通機関(JRなど)を使ってエスケープすることも、立派な戦略です。
安全対策を万全にした上で、ご自身の体力と目的に合った「お遍路と自転車」のスタイルを見つけること。それが、お大師様と「同行二人(どうぎょうににん)」で巡る、あなただけの素晴らしい巡礼体験に繋がるのではないでしょうか。
この記事が、皆さんの「幸せのかたち」を見つける旅の一助となれば幸いです。













